もし「できるだけ費用をかけずに、自分に合った方法でブログを始めたい」と本気で考えているなら、この記事はまさにご自身のためのものです。
この記事を読むことで、下の3つのメリットがあります。
- 無料ブログと有料ブログの明確な料金の違いが分かる
- レンタルサーバー代やドメイン代といった専門的な費用の内訳が分かる
- ご自身の目的に合わせて、費用で損しない最適な選択肢が分かる
この記事では、そのために不可欠な「ブログを始める費用の全知識」を、シニア初心者でも今日からすぐに理解できるよう、丁寧に解説します。
費用に関する不安を解消し、充実したブログライフへの扉を開くための一歩を、踏み出しましょう。
ぜひ最後までご覧ください。
【結論】ブログ費用は月0円か、月1,000円前後

ブログを始める費用は、目的によって「完全無料」か「月1,000円前後」の2択です。
趣味として気軽に楽しむなら無料ブログ、収益化も視野に入れるなら有料ブログが良いでしょう。
それぞれの費用感や特徴、そして「まずは無料で試したい」という方向けの方法も紹介します。
以下の項目で詳しく見ていきましょう。
選択肢①:お金をかけずに日記感覚で楽しむ無料ブログ
趣味の記録や日記として気軽にブログを楽しみたいなら、費用が一切かからない無料ブログが適しています。
金銭的なリスクを全く気にすることなく、すぐに記事を書き始められる点が最大のメリットです。
例えば、はてなブログやnoteといったサービスに登録するだけで、専門知識がなくても簡単に自分だけのブログを開設できます。
実際に多くのシニアの方が、これらの無料サービスを利用して旅行の思い出や趣味の園芸記録などを発信し、生活をより豊かなものにしています。
収益化には制約が多いものの、まずは「インターネット上で文章を発信する楽しさ」を体験してみたい方にとって、無料ブログは、まず始めるのにぴったりです。
選択肢②:収益化も目指せる月1,000円からの有料ブログ
将来的にブログを収益化し、年金の足しにしたいとお考えなら、月々1,000円程度の費用がかかる有料ブログ(WordPress)一択です。
有料ブログは独自ドメインを使用するため信頼性が高く、広告掲載の制限もないため、本格的なブログ運営に適しています。
レンタルサーバーを契約しWordPressを導入する必要がありますが、毎月の費用はサーバー代の1,000円前後です。
筆者もこの方法でブログを開設し、6年間運営を続けています。
初期投資はかかりますが、その分「本気で取り組む」という覚悟も固まります。
ご自身の資産としてブログを育て、収益化の可能性を広げたい方には、有料ブログが最良の選択肢です。
まずは無料で試してみて、本格的に続けたくなったら有料へ
どちらを選ぶべきか迷う方は、まず無料ブログで始めて運営に慣れてから、有料ブログへ移行する方法が良いでしょう。
無料ブログで「書く習慣」や「発信する楽しさ」を実感した後に有料へ移行すれば、費用を無駄にするリスクを最小限に抑えられます。
例えば「はてなブログ」で3カ月間、週1回の更新を目標に日記をつけてみてはいかがでしょうか。
そこで「続けられそうだ」「本格的に収益化したい」と感じた段階でWordPressへの移行を検討します。
多くの無料ブログサービスには、記事データをまとめて有料ブログへ引っ越しさせる機能が用意されています。
最初から大きな投資に不安を感じる方は、このステップアップ方式でご自身のペースでブログを始めるのがおすすめです。
「無料ブログ」と「有料ブログ」の費用に関する3つの違い
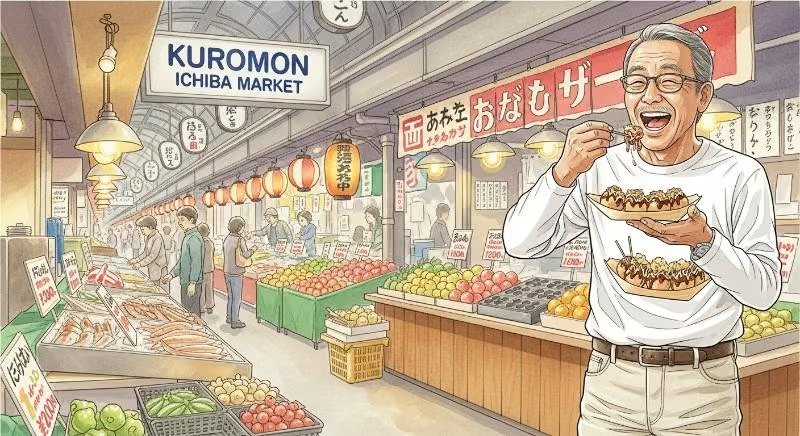
無料ブログと有料ブログで迷う最大のポイントは費用面です。
両者の費用の違いを下の3点から解説します。
- 初期費用
- 月額・年間費用
- 機能とのバランス
この違いを理解すれば、ご自身の目的に合った後悔のない選択が可能です。
一つずつ詳しく見ていきましょう。
違い①:ブログを始める時に支払う「初期費用」
ブログを始める際の初期費用は、無料ブログが0円なのに対し、有料ブログは数千円かかる場合がある点が大きな違いです。
有料ブログは「サーバー」と「ドメイン」の契約が必要ですが、最近はキャンペーンで無料になることも少なくありません。
例えば無料サービスなら、メールアドレスだけで即日開始できます。
有料ブログは通常5,000円弱かかりますが、多くの会社が無料特典を用意しています。
年金生活で初期投資を抑えたい方は、まず無料ブログで試すか、有料ブログのキャンペーンを狙うのが良い選択です。
無料ブログのメリット・デメリットの詳細については下の記事をご覧ください。
違い②:毎月・毎年かかる「月額・年間費用」
ブログ運営を続ける上で継続的に発生する費用にも、無料と有料で明確な差があります。
無料ブログは基本的に月額費用はかかりません。
有料ブログを運営するには、主にレンタルサーバーの利用料金が毎月または毎年発生します。
この月額費用は、契約するサーバーのプランによりますが、シニアの方が趣味や収益化の第一歩として始めるなら、月々1,000円前後のプランで十分です。
年間に換算すると約12,000円の出費となります。
この金額を「高い」と感じるか「自己投資」と捉えるかが大きな分かれ道です。
筆者の経験上、この費用を払うことで「元を取ろう」という意識が働き、ブログ継続のモチベーションにも繋がっています。
違い③:【一覧表】費用と機能の比較まとめ
無料ブログと有料ブログの費用と、それに伴う機能の違いを一覧表にまとめました。
ご自身の目的と照らし合わせながら、どちらがより適しているかを判断する材料にしてください。
収益化を目指すのであれば、広告掲載の自由度が高い有料ブログに軍配が上がります。
| 比較項目 | 無料ブログ | 有料ブログ(WordPress) |
|---|---|---|
| 初期費用 | 0円 | 0円~5,000円程度 |
| 月額費用 | 0円 | 1,000円前後 |
| 独自ドメイン | 利用不可 | 利用可能 |
| 広告掲載 | 制限あり | 完全に自由 |
| デザイン | テンプレート依存 | 自由自在 |
| 運営主体 | サービス提供会社 | 自分自身 |
| 資産性 | なし | あり |
このように、費用をかけない代わりに様々な制約があるのが無料ブログです。
月々の費用はかかりますが、デザインから収益化まで全てを自分でコントロールできるのが有料ブログの大きな特徴です。
ご自身のブログを大切な「資産」として長期的に育てていきたいのであれば、有料ブログを選ぶのが間違いない選択です。
有料ブログ(WordPress)にかかる3つの費用の内訳
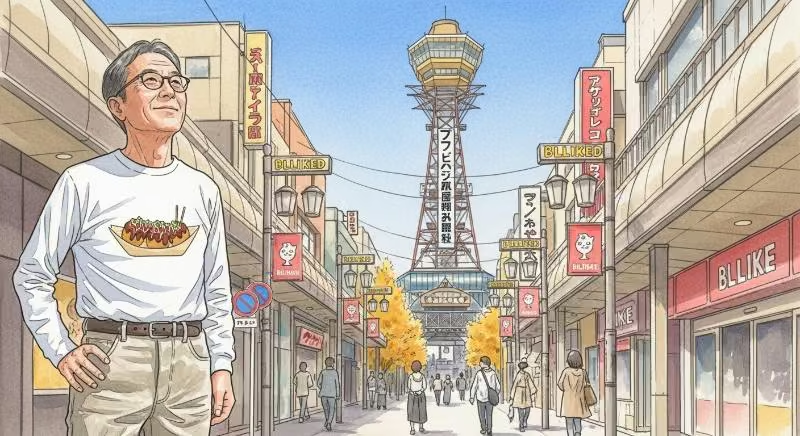
有料ブログを始める費用は主に下の3つの内訳で構成されます。
- ブログのデータを置く「レンタルサーバー代」
- ネット上の住所「独自ドメイン代」
- デザインの土台「有料テーマ代」
それぞれの役割と料金目安を把握すれば、安心してブログ運営をスタートできます。
一つずつ見ていきましょう。
内訳①:月1,000円前後からのレンタルサーバー代
有料ブログ運営で基本となるのが「レンタルサーバー代」です。
これは、作成した記事や画像を保管しておくインターネット上の「土地」を借りる費用と考えると分かりやすいでしょう。
この土地があるからこそ、世界中の人がご自身のブログにアクセス可能です。
シニア初心者の方向けのサーバーであれば、月額1,000円前後のプランで性能は十分です。
筆者もエックスサーバーを利用しています。
まずは、このサーバー代が毎月の固定費だと把握することが、ブログの費用全体を掴む第一歩になるでしょう。
レンタルサーバー3社の比較については下の記事をご覧ください。
内訳②:年1,500円前後の独自ドメイン代
次に必要なのが、ブログの「住所」にあたる「独自ドメイン代」です。
これはご自身だけのオリジナルURLを取得・維持する費用で、年間1,500円前後が目安となります。
独自ドメインを持つことで読者からの信頼性が高まり、ブログの専門性を印象づけられます。
無料ブログではサービス名が入った長いURLになりますが、独自ドメインなら短く覚えてもらいやすいのがメリットです。
最近では、レンタルサーバーを長期契約すると、このドメイン代が契約期間中ずっと無料になる特典も多くなっています。
年単位での支払いとなるため、一度設定すれば当分は安心です。
この「住所」の取得が、ご自身のブログを資産として育てるための最初の一歩になります。
内訳③:買い切り1万円台からの有料テーマ代
最後の費用項目はブログのデザインを決める「有料テーマ代」です。
これは必須ではありませんが、簡単な操作性とデザイン性の高さから利用する人が増えています。
料金は1万円台の「買い切り」が主流で、一度購入すれば追加費用は不要です。
無料テーマ(筆者が使うCocoonなど)でも十分ですが、有料テーマなら専門知識がなくてもプロ並みのデザインを簡単に実現できます。
パソコン操作に不安がある方ほど、直感的にデザインを整えられるメリットは大きいでしょう。
どのテーマが良いか迷う方は記事をご覧ください。
費用を抑えたいシニア向け!お得に始める3つのコツ

有料ブログの費用は、少しの工夫で賢く抑えられます。
特に年金生活の方にとっては、出費は少しでも減らしたいものでしょう。
ここでは、シニアの方がお得にブログを始めるための具体的な3つのコツを紹介します。
これらのポイントを押さえるだけで、年間の運営費を数千円単位で節約できます。
コツ①:レンタルサーバーの「長期契約割引」を利用する
レンタルサーバーの月額料金は、契約期間を長くするだけで大幅に節約できます。
多くのサーバー会社では、12カ月や24カ月といった長期契約を結ぶことで、月々の支払い額が割引されるプランが用意されています。
毎月支払うよりも年間総額で数千円安くなることも珍しくありません。
例えば月額1,500円のプランでも、3年契約なら月額1,000円程度まで下がる場合があります。
この差額は年間で6,000円にもなり、小さくない金額です。
最初にまとめて支払う必要はありますが、長期的にブログを続ける覚悟があるなら、この割引を最大限に活用しない手はありません。
契約時には複数の契約期間での料金を比較検討することをおすすめします。
コツ②:サーバー契約時の「独自ドメイン無料特典」を狙う
レンタルサーバーの契約時には、「独自ドメイン無料特典」の有無を必ず確認しましょう。
多くのサーバー会社が、長期契約とセットで、通常は年間1,500円ほどかかる独自ドメインを無料で提供するキャンペーンを実施しています。
この特典を利用すれば、ブログ運営に必須のドメイン代を0円に抑えられます。
エックスサーバーやConoHa WINGといった人気のサーバーでは、この特典が付いていることが多いです。
サーバーとドメインの管理会社が同じになるため、支払いや更新手続きが一本化され、管理が楽になるというメリットもあります。
費用と手間を省くためにも、この特典は見逃せないポイントです。
コツ③:高機能な無料テーマ「Cocoon」を活用する
ブログのデザインを決めるWordPressテーマは、必ずしも有料である必要はありません。
筆者がこのサイトで使っている「Cocoon」のように、無料でも有料テーマに匹敵するほど高機能なものが存在します。
有料テーマの1万円以上の初期投資を、Cocoonを選べば完全に節約できます。
Cocoonは、シンプルなデザインながら記事の装飾機能やSEO対策機能が豊富に揃っており、初心者でも扱いやすいと評判です。
利用者が非常に多いため、設定で分からないことがあっても、ネットで検索すれば大抵の解決策が見つかるのも大きなメリットです。
まずはCocoonで始めてみて、物足りなさを感じてから有料テーマを検討しても決して遅くはありません。
Cocoonについての詳細は下の記事をご覧ください。
ブログの費用についてのよくある質問

- Qパソコンやスマホ本体の費用は含まれますか?
- A
いいえ、含まれません。この記事で解説した費用は、あくまでブログをインターネット上で運営するための料金です。もしブログ用に新しくパソコンやスマートフォンを購入される場合は、その分の費用が別途必要になりますのでご注意ください。
- Qインターネット回線の費用は必要ですか?
- A
はい、必要です。ご自宅にインターネット環境がない場合は、光回線やホームルーターなどの契約が別途必要です。すでに契約済みであれば、追加の費用はかからずにブログを始めることができますのでご安心ください。
- Q無料ブログから有料ブログへの引っ越しはできますか?
- A
はい、可能です。多くの無料ブログサービスでは、記事データを書き出して有料ブログ(WordPress)に移行するための機能が用意されています。専門知識が少し必要ですが、手順を解説したサイトも多いため、挑戦する価値があるでしょう。
- Q有料ブログの支払い方法には何がありますか?
- A
主にクレジットカード払いが一般的です。その他、銀行振込やコンビニ払い、特定の電子マネーに対応しているサーバー会社もあります。ご自身の都合の良い支払い方法が利用できるか、契約前に公式サイトで確認しましょう。
- Q途中で解約した場合、返金はされますか?
- A
サーバー会社の方針によりますが、多くの場合は契約期間の途中で解約しても返金されないことがほとんどです。ただし、契約初期の数週間はお試し期間として返金保証を設けている会社もあるため、規約を確認しましょう。
- Qブログで稼げば、費用は回収できますか?
- A
はい、十分に可能です。ブログで月1,000円以上の収益を上げられれば、サーバー代などの運営費用は実質無料になります。すぐに達成するのは簡単ではありませんが、継続することで費用を上回る収入を得ることは現実的な目標といえます。
まとめ|目的と予算に合ったプランを選ぼう
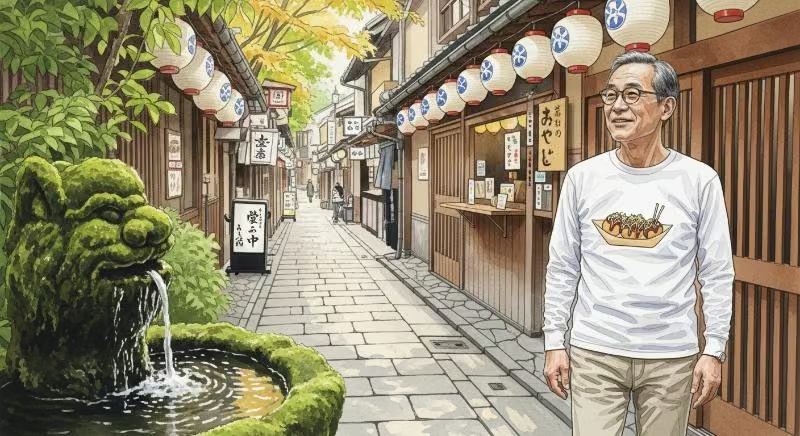
この記事では、ブログを始める際の費用について、無料と有料の違いを中心に解説しました。
重要なポイントは以下の3点です。
- 趣味なら無料ブログ、収益化も考えるなら月1,000円前後の有料ブログが目安
- 有料ブログの費用は主に「サーバー代」「ドメイン代」「テーマ代」で構成される
- 長期契約や無料特典を活用すれば、有料ブログの費用も賢く抑えられる
まずはご自身の目的に合わせて、費用をかけるべきかどうかをじっくり検討しましょう。
ブログの収益化の仕組みについて理解できたら、当サイトのシニア向けブログの始め方に関する記事もご覧ください。







