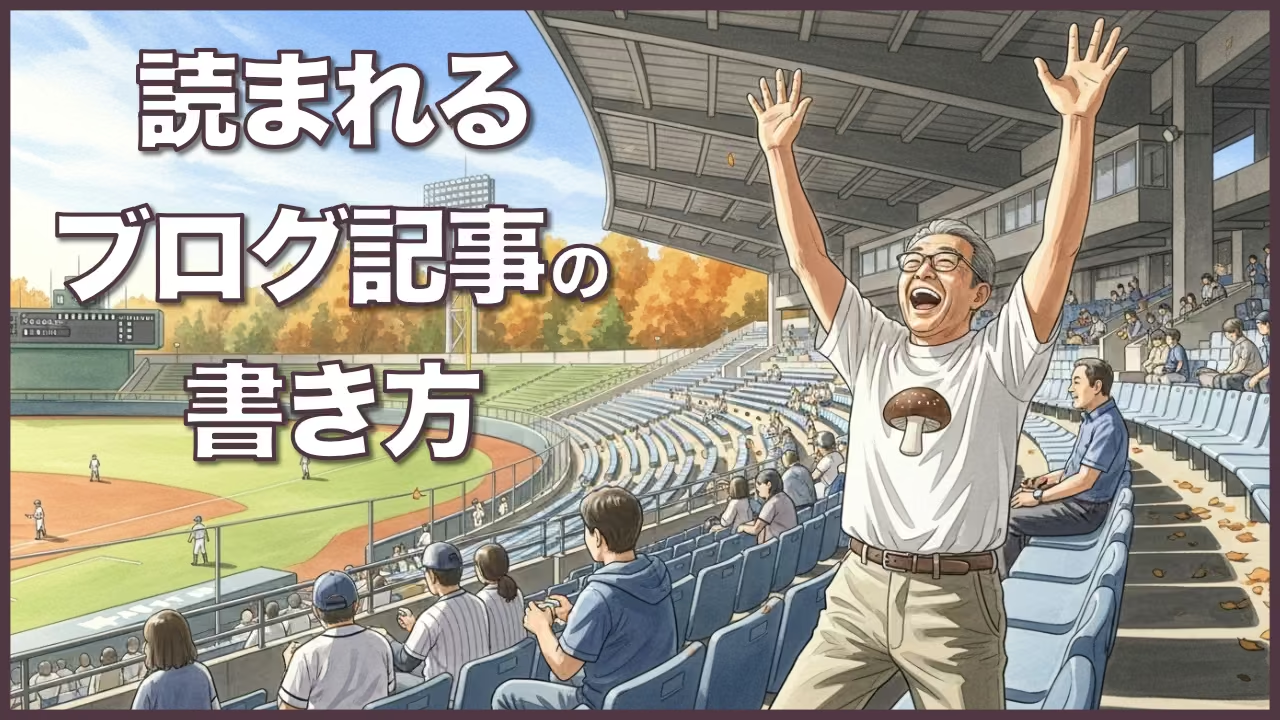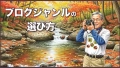ブログの文章がスラスラ書けるようになるために最も重要なのは、結論からいうと「完璧を目指さず、まずは簡単な型にはめて書くこと」です。
多くの方が「何から書けばいいか分からない」と悩むのは、文章の構成、つまり設計図がないまま書き始めようとするからです。
この記事では、なぜ「型」を使うことがそれほどまでに有効なのか、そして、ブログ歴6年の筆者が実践する、初心者でもすぐに真似できる具体的な5つのコツについて、分かりやすく解説していきます。
この記事をしっかり読めば、明日からご自身の考えを迷わず文章にするための具体的なノウハウが身につき、ブログを書くことへの苦手意識が楽しみに変わる第一歩を踏み出せます。
ぜひ最後までご覧ください。
なぜシニアはブログの文章が書けないのか?その原因とは

ブログを書こうとパソコンに向かっても、なかなか筆が進まないことがあります。
特にシニア世代の方が文章を書けないと感じるのには、いくつかの共通した原因が考えられます。
完璧を求めすぎたり、何を書くべきか迷ったり、ご自身の文章力に自信がなかったりすることが、その主な理由です。
以下の項目で、それぞれの原因を詳しく見ていきましょう。
原因①:完璧な文章を書こうと気負いすぎている
ブログを書く際に「完璧な文章でなければならない」と気負いすぎてしまうことが、書けなくなる大きな原因になります。
読者の役に立つ、誤字脱字のない文章を目指すあまり、最初の一文から手が進まなくなるのです。
特に、長年の社会人経験を持つ方は、仕事で作成する報告書のように、質の高い文章を書くことをご自身に課してしまいがちといえます。
しかし、ブログは個人的な表現の場であり、必ずしも完璧である必要はありません。
まずは完成させることを目標に、気軽に書き始める意識を持つことが大切です。
原因②:何から書けば良いか分からず手が止まってしまう
書きたいテーマはあっても、具体的に「何から書き始めるか」で手が止まってしまうのは、多くの方が経験するものです。
これは、記事全体の構成、つまり設計図が頭の中に描けていないために起こります。
例えば、家を建てる際に設計図がなければ、どこから手をつけていいか分からないのと同じ状態でしょう。
ブログ記事も同様に、まず「導入」「本文」「まとめ」といった大まかな骨組みを考え、どのような順番で読者に情報を伝えるかを決めることが必要です。
この構成を考える習慣がつけば、書き出しで迷うことは大幅に減少し、スムーズに執筆を進められるようになります。
原因③:自分の文章力に自信が持てず、公開するのが怖い
ご自身の文章力に自信がなく、「こんな文章を公開して、他の人からどう思われるだろう」という不安が、執筆のブレーキになることがあります。
これは、特にブログという不特定多数の人が閲覧するメディアにおいて、自然な感情といえるでしょう。
SNSなどで他者の優れた文章に触れる機会が多い現代では、無意識にご自身の文章と比較してしまい、自信を喪失してしまうケースも少なくありません。
しかし、ブログの価値は文章の巧みさだけで決まるものではなく、ご自身の経験や人柄が伝わる誠実な文章に魅力を感じる読者も多く存在します。
まずは「上手に書くこと」よりも「誠実に伝えること」を意識するのが大切です。
「書けない」を解消する!スラスラ書ける5つのコツ
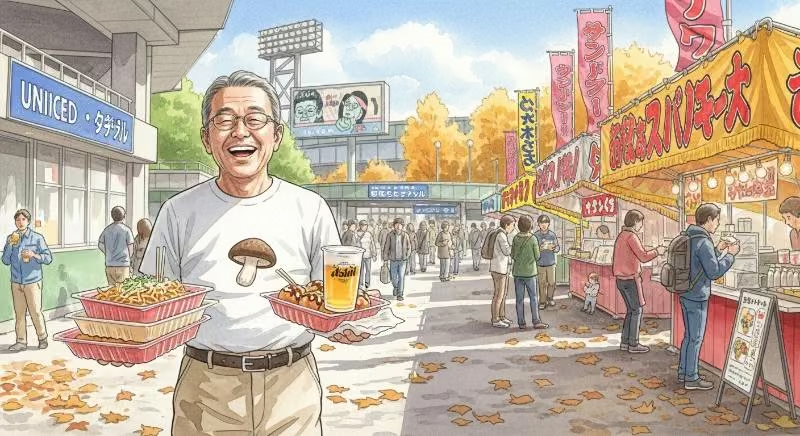
文章が書けないという悩みは、具体的なコツを知ることで解消できます。
難しく考える必要はなく、まずは普段話している言葉をそのまま文字にしてみることから始めるのがおすすめです。
構成の型を使ったり、短い文章を意識したりと、初心者でもすぐに実践できる5つの簡単なコツがあります。
以下の項目で、スラスラ書けるようになるための具体的な方法を一つずつ解説します。
コツ①:まずは「話すように」自由に書き出してみる
文章を書こうとすると固まってしまう方は、まず「話すように書く」ことを試してみてはいかがでしょうか。
これは、友人や家族に語りかけるような気軽さで、頭に浮かんだ言葉をそのまま文章にしていく方法です。
例えば、「今日はサイクリングに行ってきて、すごく気持ちが良かった」といった話し言葉を、そのままタイピングしてみるのです。
この方法の利点は、「書く」という行為の心理的なハードルを大きく下げられる点にあります。
最初は文章の構成や表現の巧みさを一切気にせず、とにかく思いのままに書き出すことで、書くことへの抵抗感をなくしていくことが、スラスラ書けるようになるための第一歩になります。
コツ②:「PREP法」という型を使って文章を組み立てる
伝えたいことがまとまらない場合は、「PREP法」という文章の型を活用するのが有効です。
PREP法とは、「Point(結論)」「Reason(理由)」「Example(具体例)」「Point(結論)」の頭文字を取ったもので、この順番で文章を構成する手法といえます。
最初に結論を述べることで、読者は話の要点をすぐに理解できます。
筆者のブログ運営経験からも、この型は非常に強力で、特にブログ初心者の方には強くおすすめします。
例えば、「ブログは楽しい(結論)。なぜなら新しい発見があるからだ(理由)。実際に先日…(具体例)。だからブログは楽しい(結論)。」のように、当てはめるだけで論理的な文章が完成します。
コツ③:短い文章を繋げることを意識して書いてみる
読みやすい文章を書くための簡単なコツは、一文を短くすることです。
長い文章は、主語と述語の関係が分かりにくくなりがちで、読者にストレスを与えてしまいます。
目安として、一文は60文字以内、句読点「。」で区切ることを意識してみてください。
例えば、「昨日は天気が良かったので、自転車で隣町の公園まで行きました」のように、一つの文章には一つの情報だけを盛り込むようにします。
短い文章を繋げていくことで、文章全体のリズムが良くなり、内容が格段に伝わりやすくなるでしょう。
文章が長くなってしまった場合は、一度立ち止まり、どこかで区切れないか確認する習慣をつけるのがおすすめです。
コツ④:100点を目指さず「60点でOK」と考える
ブログ記事を書く上で大切なのは、完璧を目指さないことです。
「100点満点の記事を書こう」と意気込むと、かえって筆が止まってしまいます。
まずは「60点で良いので、とにかく公開する」という気持ちで取り組んでみましょう。
ブログ記事は、一度公開した後でも、いつでも何度でも修正や追記が可能です。
筆者自身も、公開した記事を後から読み返し、表現を修正したり、新しい情報を付け加えたりすることは日常的に行っています。
最初から完璧な記事は存在しません。
まずは60点の完成度で世に出し、読者の反応を見ながら100点に近づけていく、というくらいの気軽な気持ちでいることが長続きの秘訣です。
コツ⑤:毎日5分でもキーボードに触れる習慣をつける
文章を書く能力は、スポーツや楽器の練習と同じで、日々の継続によって向上します。
そのため、「毎日5分でもキーボードに触れる」という習慣を作ることが、書くことへの抵抗感をなくす上で非常に効果的です。
本格的な記事を書く必要はありません。
例えば、その日にあった出来事を2〜3行の日記として書くだけでも十分といえます。
大切なのは、「書く」という行為を日常生活の一部に組み込むこと。
毎日少しずつでも文章に触れることで、タイピングの速度が上がったり、ご自身の考えを言葉にするスピードが速くなったりと、徐々に成長を実感できるでしょう。
この小さな習慣の積み重ねが、いずれスラスラと文章を書ける力に繋がります。
「書くことがない」悩みを解決するネタ探しのヒント
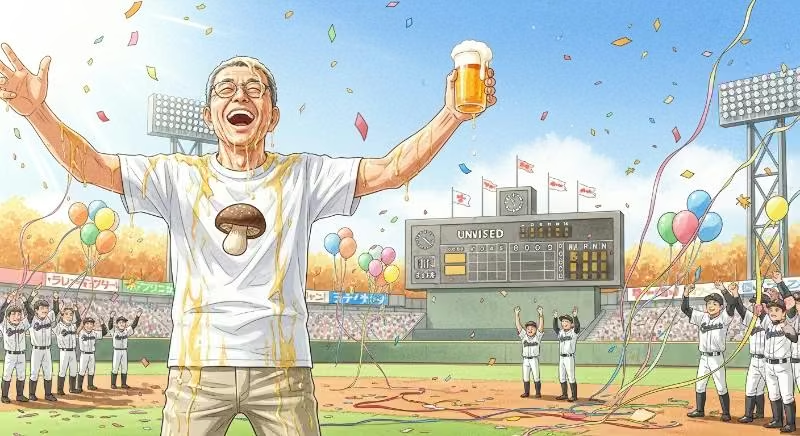
いざブログを書き始めても、「何を書けばいいのか分からない」というネタ切れの悩みは、多くの方が直面する壁です。
しかし、特別な経験がなくても、ブログのネタはご自身の身の回りにあふれています。
ご自身の好きなことや得意なことを振り返ったり、過去のご自身が知りたかった情報を思い出したりするだけで、それは立派な記事のテーマになります。
ここでは、ネタ探しに役立つ具体的な3つのヒントをご紹介します。
ヒント①:自分の「好き」や「得意」を棚卸ししてみる
ブログのネタを見つける最も簡単な方法は、ご自身の「好き」なことや「得意」なことを棚卸ししてみることです。
長年の趣味である釣りやサイクリング、好きな料理のレシピ、これまで仕事で培ってきた経験など、ご自身が夢中になれることであれば、それは読者にとっても価値のある情報になり得ます。
例えば、釣りの経験が豊富な方なら、初心者におすすめの釣り堀や道具の選び方について、誰よりも詳しく、そして情熱を持って語れるでしょう。
ご自身にとっては当たり前の知識や経験でも、他の人から見れば「知りたかった情報」であることは少なくありません。
まずはご自身の人生を振り返り、好きなことや得意なことを書き出してみることから始めましょう。
ヒント②:過去の自分が知りたかった情報を書いてみる
ブログネタを探す際には、「過去のご自身が知りたかったことは何か?」と考えてみるのも非常に有効な方法です。
例えば、ご自身がブログを始めようとした時に、何に悩み、どんな情報があれば助かったかを思い出してみてはいかがでしょうか。
「シニア向けの分かりやすいパソコンの選び方」「初めてでも安心なレンタルサーバーの契約手順」など、ご自身の過去の体験に基づいた情報は、同じような状況にいる読者にとって非常に価値のあるコンテンツになります。
筆者自身も、ブログ運営でつまずいた経験を基に記事を書くことがよくあります。
過去のご自身を助けるつもりで書いた記事は、同じ悩みを持つ読者の心に強く響き、共感を呼びやすいのです。
ヒント③:散歩や買い物など、日常の出来事をメモしておく
ブログのネタは、特別なイベントの中だけにあるわけではありません。
散歩中に見かけた美しい花の様子や、買い物で訪れたお店の丁寧な接客、日々のニュースを見て感じたことなど、ご自身の心が動いた瞬間はすべてブログのネタになり得ます。
大切なのは、それらの小さな発見や感動を忘れないようにメモしておくことです。
スマートフォンや小さな手帳を持ち歩き、「面白い」「誰かに伝えたい」と感じたことを、その場でキーワードだけでも書き留めておく習慣をつけましょう。
これらのメモが、後で記事を書く際の貴重な材料になります。
日常の些細な出来事に目を向けることで、ご自身の生活がより豊かになると同時に、ブログのネタに困ることもなくなります。
文章作成を助ける便利な無料ツールとテンプレート
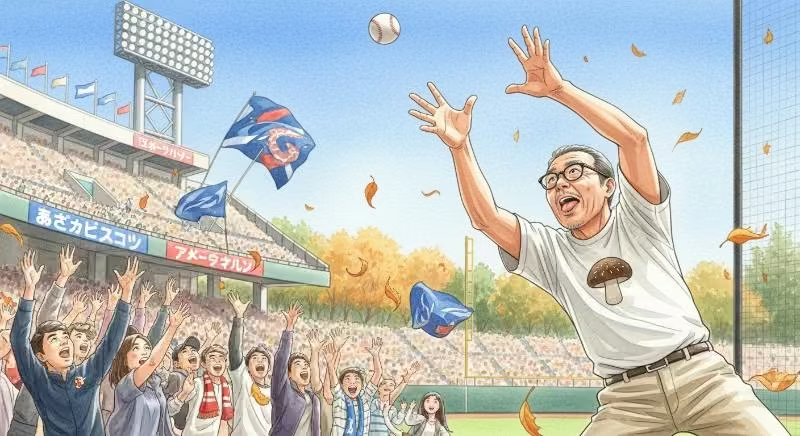
文章を書くのが苦手だと感じている方でも、便利なツールを使えば執筆の負担を大きく軽減できます。
特に、スマートフォンの音声入力機能や無料の校正ツールは、タイピングが苦手な方や誤字脱字に不安がある方にとって心強い味方です。
また、あらかじめ用意されたテンプレートを活用すれば、記事の構成で悩む時間も短縮できます。
ここでは、文章作成を助ける3つの便利なツールとテンプレートをご紹介します。
ツール①:スマホの音声入力機能で、話した言葉を文字にする
タイピングが苦手な方や、キーボードを打つより話す方が得意だという方には、スマートフォンの音声入力機能が非常におすすめです。
これは、スマホに向かって話した言葉が自動的に文字に変換される機能で、iPhoneでもAndroidでも標準で搭載されています。
メモアプリなどを開き、マイクのボタンを押して話すだけで、驚くほど正確に文章を作成してくれるでしょう。
この方法なら、パソコンの前に座る必要もなく、散歩中や家事をしながらでも、思いついたアイデアを気軽に文章として残せます。
まずは話すように文章を作成し、後からパソコンで句読点や改行を整えるだけで、効率的に記事の草稿を完成させることが可能です。
ツール②:無料の校正ツールで、誤字脱字を自動チェックする
ご自身の文章の誤字脱字や、不自然な日本語表現が気になるという方は、無料の校正ツールを活用すると良いでしょう。
これは、作成した文章をコピー&ペーストするだけで、間違いのある箇所を自動で指摘してくれるウェブサービスです。
例えば、「Enno」や「日本語校正サポート」といったツールが有名で、会員登録不要ですぐに利用できます。
これらのツールは、単純な誤字だけでなく、「ら抜き言葉」や二重敬語といった、ご自身では気づきにくい細かな表現の誤りまで見つけてくれます。
ツールによるチェックを挟むことで、文章の品質に対する不安が軽減され、自信を持って記事を公開できるようになるでしょう。
ツール③:「記事構成テンプレート」を賢く活用する
何から書けば良いか分からないという悩みには、「記事構成テンプレート」の活用が効果的です。
これは、記事の骨組みとなる見出しの型をあらかじめ用意しておく方法で、毎回構成で悩む時間を大幅に削減できます。
例えば、商品のレビュー記事なら
- 結論
- 商品の特徴
- 使ってみた感想
- メリット・デメリット
- まとめ
といったテンプレートを用意しておきます。
ご自身のブログでよく書くテーマについて、いくつかのテンプレートを作っておくと良いでしょう。
このテンプレートに沿って内容を埋めていくだけで、自然と論理的で分かりやすい構成の記事が完成します。
筆者もこの方法を多用しており、執筆の効率化に大きく役立っています。
「書けない日」があっても大丈夫!続けるための心の持ち方

ブログを続けていると、どうしても筆が進まない「書けない日」が訪れることがあります。
そんな時に大切なのは、ご自身を責めずに気楽に構えることです。
他の人のブログを読んで気分転換したり、そもそもなぜブログを始めたのか、その楽しさを再確認したりするといいです。
ブログは義務ではありません。
ここでは、書けない日と上手に付き合い、ブログを長く楽しむための3つの心の持ち方をご紹介します。
考え方①:「書けない自分」を責めずに、気楽に構える
ブログが書けない日があっても、「今日も書けなかった」とご自身を責める必要は全くありません。
プロの作家でさえ、筆が進まない日はあるものです。
書けない日は、心が疲れていたり、新しい情報を取り入れるための充電期間だったりすることも考えられます。
そんな時は、「今日は休む日」と割り切って、ブログから離れて趣味の時間を楽しむのが良いでしょう。
罪悪感を抱く必要はありません。
大切なのは、ブログを書くこと自体が嫌いになってしまわないことです。
また明日、あるいは数日後に新鮮な気持ちでパソコンに向かえば良い、くらいの気楽な気持ちでいることが、結果的にブログを長く続けるための秘訣になります。
考え方②:他の人のブログを読んで、良い刺激をもらう
書く気力が湧かない時は、インプットに時間を使い、他の人のブログを読んでみるのがおすすめです。
同じシニア世代のブロガーや、ご自身と同じ趣味を持つ方のブログを訪れてみましょう。
他の方の文章を読むことで、「こんな表現の仕方があるのか」「このテーマは面白そうだ」といった新しい発見があり、それが良い刺激となってご自身の創作意欲を掻き立てられるでしょう。
また、他のブロガーの記事にコメントを残して交流してみるのも良いものです。
筆者も、ネタ探しに困った時や気分転換したい時には、よく他のブログを拝見し、新しいアイデアのヒントを得ています。
インプットなくしてアウトプットは生まれません。
書けない日は、良質なインプットの日と捉えてみてはいかがでしょうか。
考え方③:「楽しむこと」が一番の目的だと再確認する
ブログが書けなくなった時は、一度立ち止まり、ご自身がブログを始めた当初の気持ちを思い出してみましょう。
おそらく、その目的は「収益を上げること」や「有名になること」だけではなく、「趣味の記録を残したい」「誰かと繋がりたい」といった、「楽しむこと」が根底にあったはずです。
いつの間にか、「書かなければならない」という義務感に縛られてしまうと、ブログの楽しさは半減してしまいます。
書けない日は、そんなご自身の原点に立ち返る良い機会です。
アクセス数や収益といった数字を一旦忘れ、ご自身が本当に書きたいこと、伝えたいことは何かを再確認することで、また自然と書く楽しさが戻ってくるでしょう。
まとめ|今日から「書ける人」になるための第一歩
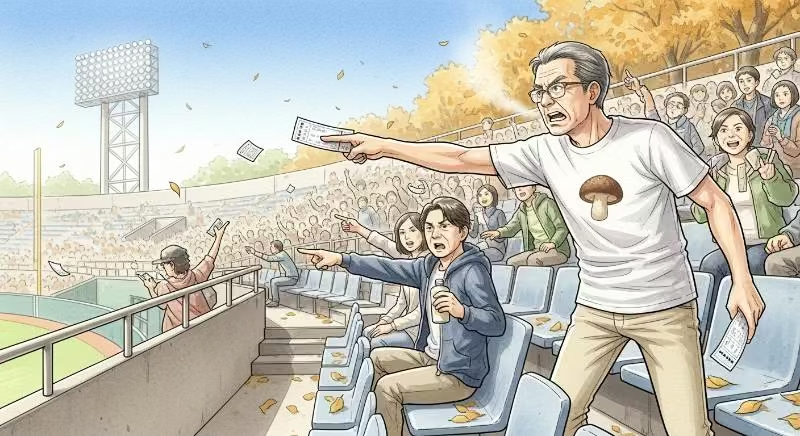
この記事では、ブログの文章が書けない原因と、スラスラ書けるようになるための5つの具体的なコツについて解説しました。
この記事でお伝えした大切なポイントは、以下の5つです。
- 完璧を目指さず「60点でOK」と考える
- 話すように自由に書き、後から修正する
- PREP法などの「型」を活用して構成に悩まない
- 一文を短くし、読みやすさを意識する
- 毎日少しでも書く習慣をつける
この記事を読んだご自身は、文章を書くことへの心理的なハードルが下がり、「自分にも書けるかもしれない」と感じていただけたのではないでしょうか。
今回ご紹介したコツは、どれも今日からすぐに実践できる簡単なものばかりです。
まずは一つでも良いので、ぜひ試してみてください。
書くことの楽しさを実感できるはずです。
当サイトでは、この他にもブログ運営に役立つ情報を発信しています。ぜひ他の記事もご覧ください。